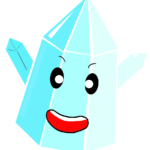フランス共和国館 鼓動と手の「愛の讃歌」 P12 エンパワーリングゾーン【万博太郎2025】-147

こんにちは、万博太郎です。
2025年の大阪・関西万博。
今回ご紹介するのは、フランスの美意識と哲学がぎっしり詰まった「フランス館」です。

テーマは「愛の讃歌」
「愛の讃歌」というとエディットピアフ

早くに両親と死別、貧困、事故、と苦労の絶えなかった人生の中で魂の歌声で
命を燃やした伝説のシャンソン歌姫です。
歌詞はエディットピアフ本人が書き上げています。
それは恋人へのメッセージ。
その恋人には妻子があり、それでも私は愛してます、
死んでも愛してますという魂の求愛のメッセージ。
2024年のパリオリンピックの閉会式でセリーヌ・ディオンが歌い、
そのまま大阪万博のフランス館のテーマにもなっている彼女の作品「愛の讃歌」
それには一体どんな意味があるのでしょう。
期待を胸にフランス館へ。
実はフランス・パビリオン、予約制ではなく並び順。
なので、朝イチ入場が叶ったこの日、真っ先に向かいました。
まだ誰も並んでいないフランス館。
静かなエントランスに掲げられたのは「鼓動」というひと言。
“何かが始まる”予感とともに、静かに館内へと足を踏み入れることができました。

ワインに込められた「成熟」という意味
展示のはじまりは、なんとワイン。
アルザス地方の名品が、まず映像で紹介されていました。

もちろん、フランスといえばワイン。
それは分かる。
だけどテーマは「愛の讃歌」なんですよね?
ただ、これは単なるフランスが誇る“お酒”の紹介ではありませんでした。
時間をかけて、土地と人に育まれていく果実。
発酵し、熟成し、やがて深い味わいをもつワイン。
それはまるで、**文化や人間そのものの“成熟”**を象徴しているように感じました。
アシタカが出迎えてくれるジブリ風の絵
その先で、見覚えのあるような絵に出会いました。

大きなキャンバスに描かれていたのは、日本の名作『もののけ姫』の一場面。
フランス人画家が描いたこの作品は、フランスのある美術賞を受賞しているとのこと。
ただの展示ではなく、これは日本文化へのリスペクト。
「フランスが日本をどう見ているか」その目線が、なんだか嬉しく、
誇らしくもありました。
「手」が語る、ものづくりの精神
次に私の心を強く打ったのは、オーギュスト・ロダンの『手』の展示です。

重厚なブロンズの作品。
容易に触れられないよう厚手のガラスケースに入れられているはいるが、
想いを伝える力がありました。
そして、その土台がまさかのルイ・ヴィトンのトランク。
“手で作られたもの”が、“手で作られた作品”を支えている。
「手でつくること」その価値が静かに、けれど確かに語られていました。
周囲には、
これまでフランスで作られてきた作品の文章や絵による紹介。
それらは日用品から発明品も含まれていました。
人々はどれだけのものを
時間をかけて
「手」で作ってきたのだろう。
そんな当たり前のことを考えさせられました。
そして、それらに現代の私たちはどれだけ助けられているのだろう。
ルイヴィトンの初期の写真
ルイヴィトンの初期のモノクロ写真が紹介されていた。

そうか、当時は現在のような革製の鞄でなく、
日本の葛籠のような、トランクのような製品から始まったことが窺えました。
そこを通り抜けると現在のルイヴィトンのカバンで形取られた大きな球体が見えてきた。
一目で地球を表していることが窺えた。

「守りの手」
次に見えてきたのが、
オーギュストロダンの初期の作品「守りの手」

古い作品で石膏でできており、とても小さかった。
この作品から始まったのか!
先ほどの傑作「手」の源を垣間見ることに心が震える。
言葉ではない、作品の展示で
まるで素晴らしい普遍の歌のようにメッセージが飛び込んでくる。
今まさに“躍動”する私たちを目覚めさせるサラウンド映像
厳かな作品を過ごすと、今度はハンパない没入感のサラウンド画面。
高所から街並みを映す壮大な映像と、屋上で踊る人々。

フランスの街を上空から俯瞰する映像に、落ちていくような足元がスウスウするような感覚
に襲われる。
まるで**“今、この瞬間を生きている”**という鼓動が伝わってくるようでした。
そうして、建物の屋上で男女三人がバレイのようなダンスを披露。
なるほど、入り口に真っ先に書かれていた「躍動」の伏線がここで回収された。
数々の作品の流れは、まさにこの躍動の連続だったのだ。
そして、私たちもその躍動の真っ最中なのだ。
厳かな水庭
エレベーターを降りると、屋外へ。
出口に広がる丸い池と再植されたばかりの木。

木はまだ枝が細く、葉もまばら。
これから半年かけて、この木は今と全然違う姿になるだろう。
なるほど、半年限りの水庭。
でもこれから半年をかけて、成長していくのでしょう。
もしかすると、池には睡蓮などが見られるかもしれない。
その変化を見届けたくて、「また来よう」と自然に思いました。
そして「分かち合う手」
そして、池づたいを歩くと、またまたオーギュストロダンの作品があった。
「分かち合う手」

そうだそうだ、この木を世話するには一人では出来ない。
物も分かち合わなくてはならないが、
労力もみんなで協力して分かち合うことは忘れてはならない。
「分かち合う手」は
協力することの尊さを象徴しているように感じました。
こちらも石膏による作品で試作のようで、
また「初心を思い出せ!」と喝を入れられているようで
身が引き締まりました。
形づくる手
再び館内へ。
またまたロダンの作品「形づくる手」が出迎えてくれました。

今度は馴染みのあるブロンズによる試作ではない立派な作品。
ロダンは何と手にこだわったアーティストだったことかと思わされた。
巨大な葡萄のオブジェ
奥へ進むと天井から吊るされた巨大な葡萄のオブジェが飛び込んできた。

入館と同時にワインがいきなり紹介され、元になるブドウがここで展示。
ワインの伏線が回収されるのと同時に、
ロダンのテーマである「手」の完成品も
これまでの小さな石膏作品から最初に見たブロンズ製の作品に至るまでの流れが、
すべて熟成という過程、
そして鼓動であると静かに物語っていた。
重なる手
ロダンの「手」はそこでは終わらず、
最後の作品「重なる手」がそこにあった。

石膏製の二つの手が重なる様子に、言葉は必要ない。
フランスよ、フランスよ、
しっかりメッセージは受け取りました。
私も”ものづくり”の端くれとして、精進し熟成して参ります。
クリスチャンディオールのドレス
その後陰影でボディラインの美しさを表現することに努めたクリスチャンディオールのドレスに出迎えられた。

しかも少しの差でそれぞれ違うデザインに仕上がっている。
これも観察眼とあくなき美の探究が成せる技だろう。
愛の讃歌
展示の最後には、ノートルダム寺院と首里城の模型。
火災で焼失した2つの建物の模型が展示。

奇しくも同じ苦しみに見舞われ、今再建に向かっている。
宗教上、全く違う立場だが、
お互い頑張ろう!
そんなシンクロニシティーを憚らずに展示する姿。
これぞ「愛の讃歌」
それを後押しするように、
モンサンミッシェルと伊勢神宮をつなぐしめ縄の模型がありました。

正に不倫の現場。
これぞ「愛の讃歌」
最後はフランスと日本の絶滅危惧種の展示。

お互い、死にそうで辛かったんだよね!
でも、表向きは環境問題への取り組みに手と手を合わそうというメッセージに見える。
これぞ「愛の讃歌」
まるで「世界中に気にせず、手を取り合おう」と語りかけてくるようでいて、
フランスジョークたっぷりの愛の讃歌でした。
フランス館がくれた、“静かな愛”
フランス館は、派手な演出はありません。
けれど、心にゆっくり染みてくる哲学と美の深さ、そしてじわじわ来る面白さがあります。
そう、まるで最近流行りの「謎解きクイズ」を解き明かすパズルのピースの展示。
そして、出来上がる「愛の讃歌」の壮大な絵のよう。
ワインで始まり、ロダンの手に導かれ、庭の木に希望を託し、
最後に“再生”と“共感”で締めくくられる構成は、まるで愛の讃歌そのもの。
展示を出たあと、私はしばらく言葉が出ませんでした。
「ありがとう、愛の讃歌。」
そう静かに、心の中でつぶやいていました。
まとめ|こんな方におすすめのパビリオン
- 芸術や哲学に興味がある人
- 落ち着いた空間で静かに感動したい人
- “手でつくること”の尊さを再確認したい人
- もう一度、何かを始めたくなっている人
あなたもぜひ、フランス館の静かな感動を体験してみてください。
コラム:よもやま話|“愛の讃歌”にまつわる連鎖する物語
エディットピアフに見出された詩人であり、歌手であり、のちに俳優となる
「シャルル・アズナヴール」
名前を聞いて、ピンと来た人もいるだろう。
そう、シャア・アズナブルの元ネタだ。
彼はその後、フランソワトリューフォーの「ピアニストを撃て!」に出演する。
題名「ピアニストを撃て!」は、西部開拓時代の酒場で、酔客を楽しませる唯一の娯楽がピアニストによる即興音楽だった頃、時折音楽に気のくわない酔客が銃弾を放つことがあった。
もし、ピアニストを撃ち殺してしまったら、娯楽がなくなるからやめてくれという意味合いで、「ピアニストを撃つな!」と酒場に張り紙があったことが由来している。
フランソワトリューフォーはの「ピアニストを撃て!」そのピアニストがひょんなことからギャング抗争に巻き込まれ、10代の少女と共に逃亡するという内容だ。
ちなみに少女役で出演するのはマリー・デュポア。
驚くほどの美人。
映画自体は幼稚なドタバタアクション映画となっているが、
のちに多大な影響を与えることとなる。
ある中年男と、若い少女がギャングから逃げるというのは、
日本では映画版「探偵物語」、同じくフランス映画の「レオン」など、
数多くの映画のデフォルトスタイルとなった。
そんな訳で、「ピアニストを撃て!」という方が古い方には馴染みがあるかもしれないが、
本当の元ネタは西部開拓時代の「ピアニストを撃つな!」という張り紙が酒場に貼らていた逸話をオスカーワイルドという詩人が持ち帰ったことに由来する。
そうして、この元ネタそのままの「ピアニストを撃つな!」というタイトルでエルトンジョンは1973年にアルバムを発表する。
エルトンジョンの人気は正に飛ぶ鳥を落とす勢い。
それまで厳かなサウンド、バーニートーピンの斬新な詩で音楽会を席巻していたが、
この「ピアニストを撃つな!」でクロコダイルロックをはじめとしたポップ路線にも切り込んでいく。そうして子供に最も聞かせたくない音楽として叩かれ始めるのと同時に
「ピアニストを撃つな!」
もし、ピアニストを撃ち殺してしまったら、娯楽がなくなるからやめてくれという意味合いは本当にジャストタイミング。
後にエルトンジョンはエディットピアフに捧げる歌も発表しており、
フランス館の放つ「愛の讃歌」は
ワインのような芳醇な香りをいつまでも放っていた。