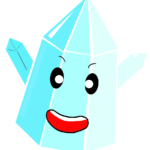X05|いのち動的平衡館 — 白い炎で“いのち”を知る【現地ミニガイド】

はじめに
外はアメーバのような膜、内は静かな暗闇。
やがて中央の装置**「クラスラ」が白だけ**の光で目を覚まし、生命のうねりが始まります。
——派手さではなく、からだの奥に火を点す展示でした。

行でわかるポイント
福岡伸一の語りが核:利他の進化/動的平衡/いのちは有限
柱なしの膜構造+完全暗転からの“白い炎”(クラスラ)
32万個のLEDが単細胞→海→陸→空→ヒトを連続で描く

体験の流れ(最短版)
動的平衡=壊しつつ作り続けることで秩序が保たれる/いのちは有限だから輝く
暗闇→点灯:白のみの光で視覚と内耳を整える
生命の連なり:生き物たちが“色ではなく運動”で立ち現れる
語りの芯:
三つの転換=原核→真核/単細胞→多細胞/無性→有性(どれも支え合い=利他が鍵)
こんな人におすすめ
科学と哲学の**“間”**にある余韻を味わいたい
静けさから入る展示が好き
解説より体感で腑に落ちたい
ひとことレビュー
壊しては作る、作っては壊す。
止まらないから、保たれる。
終わりがあるから、次が生まれる。
簡易評価(★5)
- 印象に残るか:★★★★★
- 内容の深さ:★★★★★
- 展示の完成度:★★★★★
- リピートしたい度:★★★★★
- 技術革新度:★★★★☆